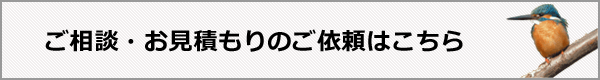アスベストの見分け方|使用されている建材や対処法も紹介

アスベストとは
アスベスト(石綿)は、天然に産する非常に細い繊維状の鉱物の総称です。耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性に優れ、安価であることから、昭和30年代から平成初期にかけて、断熱材・耐火被覆材・スレート材など建築や工業分野で幅広く使用されました。
しかし、その微細な繊維は空気中に浮遊しやすく、吸入すると長期間を経て健康被害を引き起こすことが明らかになり、日本では2006年に製造・使用・輸入がほぼ全面的に禁止されています。
現在も規制前の建物や製品には残存している可能性があり、解体や改修の際には事前調査と適切な処理が必要です。
アスベストの見分け方は専門家でも難しい理由
アスベストは、肉眼や一般的な目視だけで判別することが非常に困難な物質です。使用されている建材の種類や製造時期、経年劣化の進行具合によって色や質感が変化し、同じアスベスト含有建材でも外観が大きく異なる場合があります。さらに、アスベストを含まないにもかかわらず、外観や質感が酷似した建材も多く存在します。
こうした理由から、アスベストの有無を正確に判断するためには、専門的な知識を持つ調査員によるサンプリングと、偏光顕微鏡や位相差顕微鏡などを用いた詳細な分析が不可欠です。誤った判断で建材を破損させると、アスベスト繊維が空気中に飛散し、周囲の環境や健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、自己判断や無資格での作業は避け、必ず専門業者へ依頼することが重要です。
アスベスト含有の疑いがある建材の特徴と種類
アスベストはその耐熱性・耐火性などから多種多様な建材に使用されていました。以下は、特にアスベスト含有の可能性が高い建材とその特徴です。これらの建材はいずれも、目視や触覚だけでは判断できないケースが多く、かつ粉じん飛散リスクもあるため、慎重な取り扱いが必要です。
吹き付け材
- 外観は綿状・もこもこしており、色は青・灰・白・茶など幅広い。
- 表面に小さな隙間が見られ、柔らかく触れると繊維がほろほろと崩れる感触があります。
- 特にアスベストを含む吹き付け建材は、誤って触ったり破損すると粉じんが飛散しやすい高リスク建材です。
内装材
- 軽量で加工しやすいことから、内装の下地材として多用された石膏ボードにはアスベスト入りのものも存在します。
- 比較的「飛散リスクが少ない(レベル3)」とされる建材ですが、それでも接着剤や仕上げ材に含有している場合もあるため注意が必要です。
外装材
- 耐久性や耐火性を求められる屋根材・外壁材としてスレートや波板が採用されており、アスベスト含有タイプも広く流通していました。
- とくに古い建物ほどその可能性が高いので、外壁の劣化やひび割れなどが見られる場合は要注意です。
床材
- ビニル床タイル(Pタイル)や長尺塩ビシートは接着剤にアスベストが含まれているケースがあるため、主材だけでなく接着部分の調査も必要です。
- 下地調整材や塗床材にも含有の可能性があるため、床全面の「材質+施工歴」に基づいた分析が求められます。
保温材
- ボイラーや配管などの熱を遮断したい部分に巻き付ける用途で使用されていました。
- 状態によってはウール状・スポンジ状・ゴム状など様々な形態を持ちます。
アスベストの見分け方
アスベストは、外観や質感だけで完全に判別することは困難ですが、目視によって「疑いのある建材」をある程度見極めることは可能です。たとえば、天井や壁に吹き付けられた仕上げ材では、繊維が絡み合った綿状の表面や、ざらざら・もこもことした質感が見られることがあります。屋根や外壁に使われるスレート材では、薄く平たい板状で波型や平板の形をしており、色はグレー系が多い傾向にあります。床に敷かれたビニル床タイルでは、硬質で光沢のある表面を持ち、パターン模様や単色仕上げのものなどバリエーションも豊富です。
こうした特徴に加えて、施工された年代や製造時期も判断材料の一つとなります。特に、アスベストの使用が規制される以前の2006年より前に施工された建物や設備は、含有の可能性が高いと考えられます。工場、学校、公共施設、集合住宅など、大規模建築物ほどアスベストが広範囲に使用されていたケースも珍しくありません。
しかし、見た目だけでアスベストの有無を確実に判断することはできません。経年劣化や再塗装、汚れの付着によって外観が変化するほか、アスベストを含まない建材でも質感や色味が酷似している場合が多くあります。
このため、最終的な判定には専門業者によるサンプリングと顕微鏡分析が不可欠です。正しい分析によって初めて、アスベストの有無や種類、含有率を明確にすることができます。自己判断での解体や加工は、アスベスト繊維の飛散リスクが高く危険ですので、必ず専門機関へ依頼することが重要です。
専門機関への依頼が必要な場合は、ぜひ東海テクノにご相談ください
アスベストとよく間違われる素材
アスベストは外観が似ている素材と混同されることがあります。その代表が、ロックウール(岩綿)とグラスウールです。いずれも断熱や防音目的で広く使用されてきた人工繊維ですが、成分や繊維の太さ、安全性はアスベストとは異なります。
ロックウールの特徴
ロックウールは、玄武岩などの岩石を高温で溶かし、繊維状に加工した人工鉱物繊維です。繊維の直径は3〜10μm程度と比較的太く、触れると粉々に崩れる傾向があります。外観は白〜灰色で、ふわふわとした綿状や板状に成形された製品が多く見られます。お酢などの酸をかけると溶けることがあるのも特徴です。国際がん研究機関(IARC)では「発がん性は分類できない(グループ3)」と評価されており、通常は安全な素材です。ただし、1980年代以前に施工された吹付けロックウールにはアスベストが混入している場合があり、この場合は外観だけでは見分けがつきません。
グラスウールの特徴
グラスウールは、ガラスを溶かして繊維状に加工した断熱材で、淡黄色や白色をしており、柔らかいものから板状まで形態はさまざまです。繊維は比較的太く、触るとチクチクした感触があるのが特徴です。こちらもIARCで「グループ3」と評価され、安全性の高い素材です。アスベストのような極細繊維ではないため、肺に深く入り込みにくいとされています。
ロックウールもグラスウールも、いずれも外観や質感がアスベストと似ており、特に劣化や汚れが進んだ場合は判別が難しくなります。そのため、見た目だけで判断せず、疑わしい場合は必ず専門機関による分析を行うことが重要です。
アスベストへの対応は、まず事前調査から
アスベストは、見た目だけでは判別が難しく、含有しているかどうかは専門的な分析を行わない限り確定できません。そのため、建物の解体・改修・補修といった工事を行う際には、着工前に必ずアスベスト含有の有無を調査することが法律で義務付けられています。
事前調査では、建材の種類や施工年代、設計図書などの資料確認に加え、必要に応じて現場からサンプリングを行い、顕微鏡分析で有無と種類、含有率を特定します。こうした調査は、法令に基づく資格を持つ調査者が担当し、適切な方法で行う必要があります。
アスベストが含まれていることが判明した場合は、除去・封じ込め・囲い込みなどの工法を選定し、作業計画書の作成や関係機関への届出を経て、資格を持つ作業者が厳重な飛散防止措置を講じて作業を進めます。
「工事を始めてから見つかる」では遅く、余計なコストや工期の遅延につながる可能性があります。安全でスムーズな工事のためにも、計画段階でのアスベスト事前調査は欠かせません。
アスベスト分析は東海テクノにおまかせください
アスベストの正確な判定には、適切なサンプリングと高精度な分析が不可欠です。当社・東海テクノは、環境分析の専門機関として培ってきた豊富な経験と実績を活かし、アスベスト調査から分析まで一貫して対応しています。
建材の種類や施工状況に応じて、JIS規格に準拠した手法で分析を実施。疑いのある建材はもちろん、複層構造の材料や劣化が進んだサンプルにも対応可能です。分析結果は、報告書としてわかりやすくまとめ、今後の対応方針の判断材料としてご活用いただけます。
また、調査段階から工事計画に必要な情報提供まで、法令や安全管理の観点を踏まえた総合的なサポートを行っています。解体・改修を予定している事業者様や、所有建物の安全性を確認したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
アスベストは、かつて優れた建材として幅広く利用されてきましたが、現在では健康被害の危険性から使用が禁止されています。見た目だけで判別することは難しく、非含有の素材と混同されることも多いため、正確な判定には専門的な調査と分析が不可欠です。
特に、2006年以前に建築された建物や設備では、アスベスト含有の可能性が高く、解体・改修・補修といった工事の際には法令に基づく事前調査が義務付けられています。調査結果に応じて適切な工法と安全管理を行うことで、健康被害や環境への影響を防ぐことができます。
安全な工事と安心できる建物利用のために、疑わしい建材を見つけたら自己判断せず、必ず専門機関へ相談しましょう。アスベスト調査・分析のプロである東海テクノが、確かな技術と経験でお応えします。