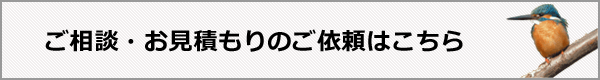リスクアセスメント対象物質とは?法規制や実施義務も解説

リスクアセスメント対象物質とは
工場や研究所、建設現場など、多くの職場ではさまざまな化学物質が使われています。その中には健康への影響が懸念されるものもあり、安全に取り扱うために、企業には「リスクアセスメント(危険性の評価)」の実施が義務づけられています。
特に注意すべきなのが、「リスクアセスメント対象物質」と呼ばれる、労働安全衛生法でリスク評価の実施が義務づけられている化学物質です。現在その数は1,000種類以上にのぼり、アセトン、トルエン、ホルムアルデヒドなど、身近な物質も多く含まれています。
また、令和5年4月には労働安全衛生法の改正により、新たな化学物質規制が導入され、化学物質に関するリスク管理の考え方が大きく変わりました。これまでのように国が指定した有害物質だけを規制する方法では限界があるとして、事業者が自らリスクを把握し、管理する“自律的な取り組み”が求められるようになりました。
リスクアセスメント対象物質一覧
これらの物質の詳細な一覧は、厚生労働省が提供する「職場のあんぜんサイト」や「ケミサポ」などの公式ウェブサイトで確認できます。これらのサイトでは、物質名、化学式、CAS番号、含有率の閾値などが掲載されており、検索機能を利用して特定の物質を調べることも可能です。
リスクアセスメントを適切に実施するためには、これらの情報を活用し、使用する化学物質の危険性や有害性を正確に把握することが重要です。また、作業手順の見直しや安全対策の強化にも役立てることができます。
最新の情報や詳細な一覧については、厚生労働省の公式ウェブサイトや関連機関の資料をご参照ください。
令和5年以降のリスクアセスメント法規制のポイント
令和5年に改正された労働安全衛生法は、随時施工されており、具体的には以下のようなポイントが強化されました。
① 対象物質が大幅拡大
GHS分類に基づき危険性・有害性が確認された約2,900種類の化学物質が新たに対象となり、ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントが義務化されました(従来は約670種)。使用している化学物質のSDSを見直し、新たに対象となった物質がないか定期的に確認しましょう。
② リスク低減措置が義務化
リスク低減措置の実施が義務化され、ばく露濃度を一定基準以下に抑えることが求められるようになりました。測定データを活用し、換気・密閉・工程変更などの具体的な低減対策を検討してください。
③ 記録・周知の強化
取った対策内容やばく露の結果を記録し、労働者の意見を聴取のうえ周知・3年間保存(がん原性物質は30年間)することが義務化されました。記録のテンプレートを整備し、保存期間と保管方法をあらかじめ社内でルール化しておくと安心です。
④ 専門担当者の選任義務
事業場ごとに化学物質管理者および保護具着用管理者(該当作業がある場合)を選任し、化学物質の評価・対策・教育・管理まで一貫して対応する体制が必要となりました。担当者の資格・知識を確認し、必要に応じて外部研修や講習の受講を検討しましょう。
⑤ 衛生委員会での審議強化
衛生委員会では、リスクアセスメントの結果、ばく露低減措置の実施状況、健康診断の結果などを議題に取り上げ、継続的に監視・改善していくことが義務化されました。衛生委員会の議事録に化学物質関連の審議内容を必ず記録し、改善の履歴が追えるようにしておきましょう。
⑥ 保護具使用の義務明確化
特に皮膚障害や眼・呼吸器への有害性が強い物質では、保護眼鏡や手袋、保護衣などの使用が義務化され、「努力義務」から法的義務に強化されました。現場での使用状況を定期的に巡回確認し、不備があればすぐに是正できる仕組みを整えましょう。
2025年以降には、さらに規制強化が予定されており、対象物質の拡大や請負現場での周知義務などが新たに加わることがわかっています。
リスクアセスメントの実施時期
リスクアセスメントの実施を求められる時期は以下のようなタイミングが挙げられます。
作業手順の変更時
作業手順や工程に変更がある場合、リスクが変化する可能性があるため、再評価が求められます。
労働災害の発生時
労働災害が発生した場合、過去のリスクアセスメントに問題がなかったかを確認し、必要に応じて再実施します。
新たな情報の入手時
SDS(安全データシート)などで新たな危険有害性の情報が提供された場合、リスクアセスメントの見直しが必要です。
定期的な見直し
機械設備の経年劣化や労働者の入れ替わりなどにより、リスクの状況が変化する可能性があるため、定期的なリスクアセスメントの実施が推奨されています。
実施義務と努力義務
リスクアセスメント対象物質による健康被害のリスクを未然に防ぐためには、「何が、どれだけ危険なのか」をあらかじめ把握し、作業環境や手順を見直すことが不可欠です。
先述のとおり、リスクアセスメント対象物質を取り扱う際には、事業者に対し、リスクアセスメントの実施が法令上義務づけられています。労働安全衛生法に基づき、化学物質の危険性・有害性を把握し、そのリスクに応じた対策を講じることは、労働災害や健康被害を未然に防ぐために不可欠な措置です。
さらに、新たな化学物質を採用する場合や、既存の化学物質・作業方法を変更する場合にも、その都度リスクアセスメントを実施し、リスクの見直しと対策の再検討を行うことが求められます。加えて、これまで努力義務とされていた項目の一部が、今後は実施義務へと段階的に移行する方針が示されています。 事業者には、法改正の動向を注視し、制度変更に迅速に対応する姿勢が求められます。
リスクアセスメントは単なる形式的な作業ではなく、労働者の安全と健康を守るために、すべての事業者が果たすべき基本的な責務であることを、ぜひご認識ください。
まとめ
近年、化学物質の取り扱いをめぐる法制度は大きく変化しており、リスクアセスメントの重要性が一層高まっています。アセトンやトルエンといった身近な物質も含まれる「リスクアセスメント対象物質」は1,000種を超え、令和5年の法改正以降は、国による一律の規制だけでなく、事業者自らがリスクを見極めて管理する“自律的な対応”が強く求められるようになりました。
リスクアセスメントは、「何がどれだけ危険なのか」を把握し、それに応じて作業環境や手順を見直すことが基本です。これは単なる形式ではなく、労働者の命と健康を守るための最前線の取り組みであり、作業手順の変更や新たな物質の採用時、災害発生時など、あらゆる場面で柔軟かつ確実に実施されるべきものです。
さらに、これまで努力義務とされてきた一部の項目も、今後は法的な実施義務へと移行することが決まっており、リスク管理の「質」が問われる時代に入っています。
制度改正に正しく対応できるかどうかが、企業としての信頼性、安全文化、そして働く人の安心感に直結します。
リスクアセスメントは単なるチェックリストではありません。現場で働く人々の安全と、企業の持続可能な運営を支える“責任ある行動”なのです。
ぜひこの機会に、自社の対応を見直し、法令遵守を超えた“安全への先手”を打っていきましょう。
東海テクノでは、化学物質の分析を専門とする環境分析の会社として、法令遵守と労働者の健康確保を支えるリスクアセスメントの実施もサポートしています。
リスクアセスメントの一環として必要となる作業環境測定や個人ばく露測定にも対応しており、実際の作業現場に即した評価と、的確な改善提案をご提供いたします。
今後も、法改正や現場ニーズに合わせたサービスの拡充を図り、お客様の安全管理体制の強化に貢献していく所存です。
化学物質を取り扱う事業者の皆様にとって、「信頼できるリスク管理のパートナー」としてお役に立てるよう、専門性と柔軟な対応力をもって支援してまいります。
リスクアセスメントに関するお困りごとがございましたら、ぜひ東海テクノへご相談ください。