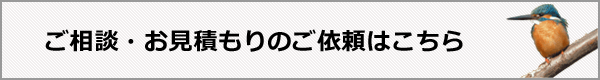サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラル!関係性などを解説

「サーキュラーエコノミー」と「カーボンニュートラル」は、持続可能な未来を目指す上で密接に関連する概念です。本記事では、資源の再利用とCO2排出削減の重要性を解説し、これらがどのように連携して環境保護に貢献するのかを詳しく紹介します。
サーキュラーエコノミー(循環経済)とは
サーキュラーエコノミー(循環経済)は、物を「作って、使って、捨てる」という従来のリニア型経済から転換し、資源をできるだけ無駄にせず、循環させる仕組みです。製品や材料のライフサイクルを長く保つために、再利用やリサイクルが重視されます。また、新しい商品を生み出す際にも、環境への負担を減らすことが考慮されます。これにより、廃棄物の削減や資源の持続可能な活用が促進され、地球環境への負荷を減らすことが期待されています。
サーキュラーエコノミーの特徴は、単なるリサイクルに留まらず、製品の設計段階から持続可能性を考慮し、資源の有効活用を追求することにあります。これにより、製品のライフサイクルが延びるだけでなく、新たな経済的価値が生まれる可能性があります。
カーボンニュートラル(脱炭素)とは
カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出と吸収のバランスを取り、全体の排出量をゼロにすることを目指す取り組みです。
具体的には、化石燃料の燃焼や工業活動で排出される二酸化炭素(CO₂)、N₂O、フロンガスなどの温室効果ガスを、森林などの自然吸収源や技術的な手法で取り除くことが含まれます。カーボンニュートラルの達成は、地球温暖化を抑え、将来世代のために持続可能な地球環境を維持するために不可欠です。
特に、日本では2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標が掲げられており、これは国全体での取り組みが求められています。エネルギー生産や輸送、産業分野での技術革新が重要であり、再生可能エネルギーの活用や、省エネルギーの推進、さらにはカーボンオフセット(他の場所でのCO₂削減活動による相殺)が具体的な方策となります。
また、個人レベルでも、省エネ家電の使用や再生可能エネルギーの選択など、小さな行動がカーボンニュートラルへの貢献となります。
サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの関係性は?
前述いたしましたサーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルですが、持続可能な社会を目指す上で深く関連しています。
サーキュラーエコノミーは、資源の使用を最小限に抑え、廃棄物の発生を抑制しながら、リサイクルや再利用を通じて資源を循環させる仕組みです。これにより、資源採掘や製造の際に発生する温室効果ガスの削減が期待されます。
例えば、製品のライフサイクル全体でエネルギーや資源消費を抑えることにより、CO₂の排出量を大幅に減らすことができます。さらに、資源の有効利用と廃棄物削減は、地球温暖化対策にも寄与し、カーボンニュートラルの達成に向けた重要なステップとなります。
サーキュラーエコノミーの考え方には「Narrowing the loop(資源消費を抑える)」「Slowing the loop(製品を長く使う)」「Closing the loop(資源を再生して使う)」といった3つのアプローチがあり、それぞれが温室効果ガス排出削減と連動しています。これにより、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーは互いに補完し合う関係性にあるのです。
世界の取り組み状況について
サーキュラーエコノミーに取り組むことで、カーボンニュートラル達成ひいては環境保護への貢献へつながることが分かりました。では、世界各国ではどのような取り組みがされているのか、一例としてEUとアメリカにおける内容を紹介していきます。
EUの取り組み
EUは「サーキュラーエコノミー行動計画」を通じて、消費者の「修理する権利」を導入し、製品の修理や長期使用を推奨しています。また、2023年にエコデザイン規則案が合意され、耐久性やリサイクル可能性を高める製品仕様の義務化が進められています。さらに、マイクロプラスチックの削減やファストファッションの規制など、環境への影響を考慮した製品政策が展開されています。
アメリカの取り組み
アメリカでは、2021年に「国家リサイクル戦略」を発表し、2030年までにリサイクル率を50%に引き上げる目標を掲げています。リサイクル品の汚染防止や、リサイクル施設での機械選別技術の活用に力を入れており、特に分別の負担を軽減しつつ効率を高める取り組みが進んでいます。
両国とも、廃棄物削減とリサイクル効率の向上を目指しており、サーキュラーエコノミーの実現に向けた先進的な政策を展開しています。
今後どのように取り組むべきか?
ではサーキュラーエコノミーの実現に向け、日本はどのように取り組みを進めていくべきか考えてみましょう。
1. 事業者
企業はリサイクル素材の活用目標を設定し、サプライチェーン全体で協力して資源を循環させることが重要です。また、政府と協力して製品の耐久性向上やリサイクル促進のためのルール改正を提案することも推奨されます。
2. 自治体
自治体は、リサイクル施設の整備を進め、焼却に頼らない廃棄物処理の仕組みを構築する等の取り組みを行う必要があります。10年単位の長期計画で、廃棄物の資源化を進めることが大切です。
3. 消費者
消費者は、「ごみの分別」への協力だけではなく壊れやすい製品を避け、リサイクルに出す際は洗浄を十分に行う等リサイクルが出来るような状態にすることが重要です。また、サービス化やデジタル化等が進む中で、モノを所有せず、シェアリングなどを利用する新しいライフスタイルも推奨されます。
4. 学識者、投資家
学識者は科学的な調査を通じて政策提言を行い、投資家は資源循環を評価基準に加え、循環経済に取り組む企業への支援を促進することが必要です。
このように各立場に合わせて、カーボンニュートラルの目標達成に向けて様々な取り組みを行うことが可能です。これらの取り組みを行うことで、サーキュラーエコノミーを実現しつつ、カーボンニュートラルの目標達成に向けて日本はさらに進むことができると考えられます。
まとめ
サーキュラーエコノミーは資源の無駄を最小限にし、再利用を重視する経済モデルであり、カーボンニュートラルの達成に貢献します。製品のリサイクルや再利用によってCO₂排出を削減し、持続可能な社会を築くために役立ちます。
EUやアメリカは先進的な政策を展開しており、日本も企業がリサイクル素材を積極的に活用し、自治体がリサイクル施設の整備を進め、消費者が壊れにくい製品を選ぶなど、全体でサーキュラーエコノミーの実現に向けて取り組むことが大切です。私たちが意識をもって行動することより、持続可能な社会への移行がより促進されるのではないでしょうか。